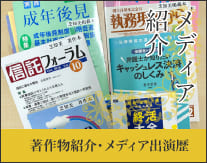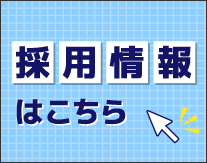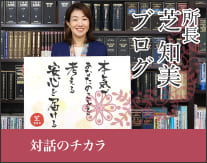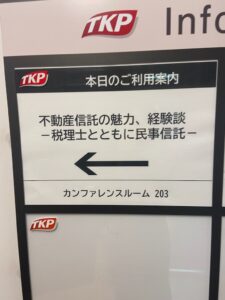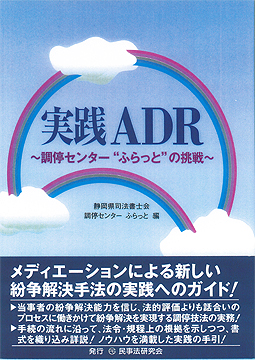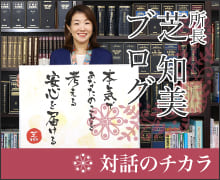滞納をすると再生債権者の申立により再生計画が取り消されてしまうかもしれませんが、場合によっては返済を延長できる可能性はあります。
また、一定の要件を満たせば残りの支払いを免除できる場合もあります。
個人再生は借金を減額する措置なので、認可された後は再生計画に基づいて返済をする必要があります。
もし、滞納をしてしまうと、再生債権者は再生計画取消の申立を行うことができ、個人再生が取り消されると、個人再生そのものがなかったことになります。
減額された借金は元の金額に戻り、その金額を支払わなければなりません。
しかし、会社の倒産やリストラ、ケガや病気などによる休養など、やむを得ない事情によって再生債権の返済が難しくなった場合で、それまでの返済方法では支払いがどうしても継続できない状態にある場合は、裁判所に申立てを行うことによって、返済期間を一定程度延長することができます。
延長できる期間の上限は2年間で、期間が延長されると、返済総額は変わりませんが、毎月返済していく金額は少なくなるため、返済負担を軽減できます。
また、非常に厳しい条件が要求されているハードシップ免責という制度があり、この制度を利用すると、残りの借金の支払い義務の免除を受けることができます。
その条件とは、
1.病気やケガ、リストラなど再生債務者がその責めに帰することができない事由が生じたこと
2.長期間収入がなくなり、再就職が難しいなど、将来にわたり 返済が極めて困難であること
3.再生計画の返済金額の4分の3以上が返済済みであること
4.債権者の一般の利益に反するものでないこと
5.再生計画の変更により返済期間の延長をしても返済ができないと認められること
上記の4は、現金の他、株式などの有価証券、生命保険の解約返戻金、その他価値のある動産などを現金に換えた場合に、債権者に配当される金額以上を免責の際に返済していなければいけないとされています。
ハードシップ免責によりすべての債務は免除されますが、住宅ローンも免除されるため、住宅ローンの債権者は残りの支払いを受けることができなくなります。
その結果、債権者は抵当権を実行して住宅を競売にすることができ、住宅を守りながら債務を返済していくという個人再生のメリットが生かせなくなってしまいますので、注意が必要です。
借金のことで悩んでいて債務整理をお考えの場合、個人再生も含め、現在の生活状況や負債状況に合わせた債務整理の方法をご提案致します。
是非芝事務所へご連絡下さい。
司法書士 三浦和弥