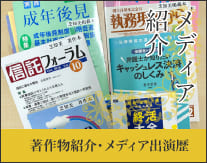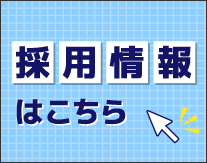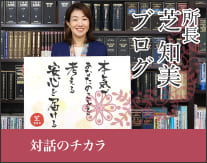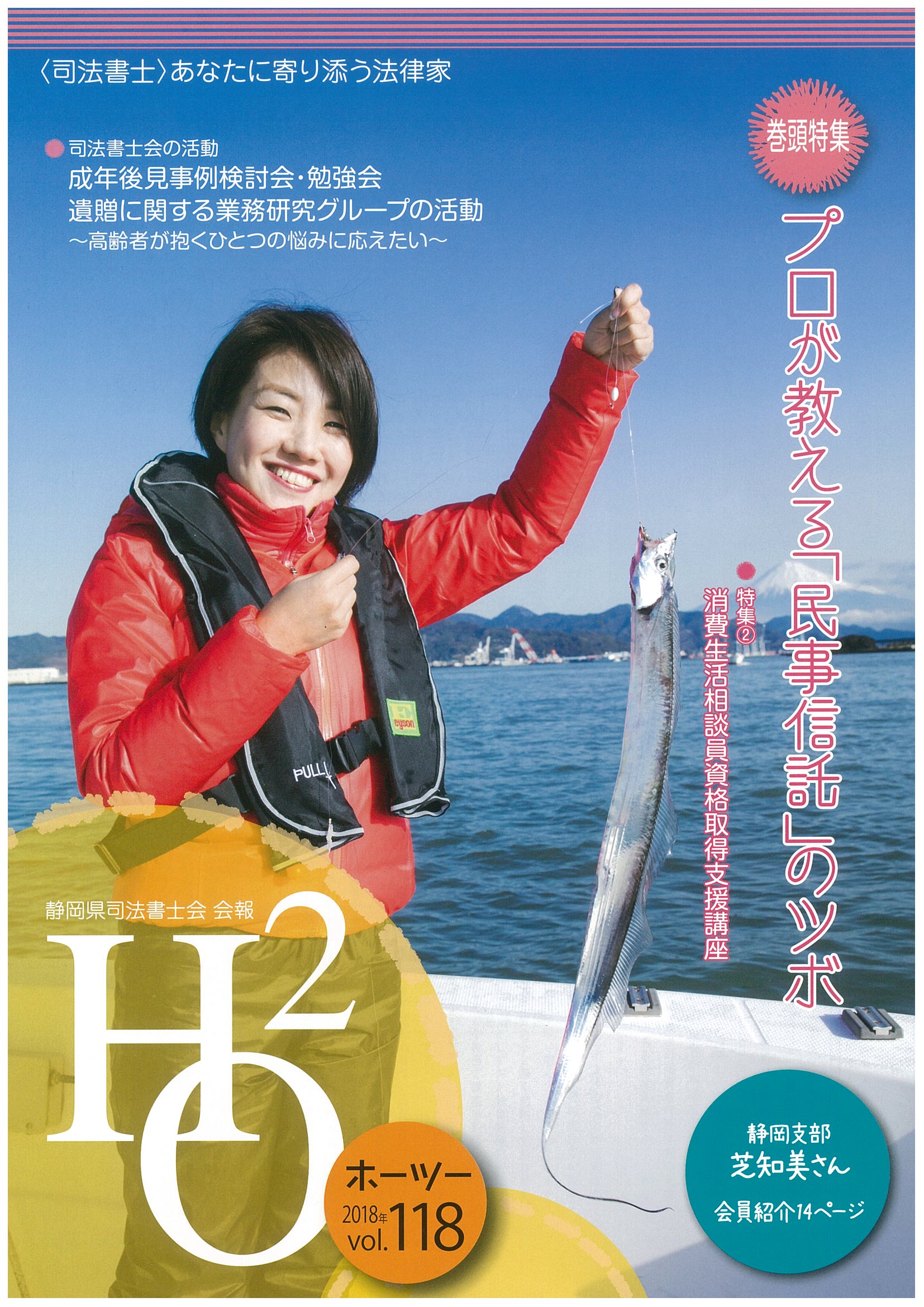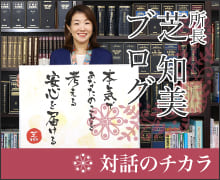こんにちは、スタッフの杉本です。
夏日がきたと思ったらまた寒くなりましたね。
みなさん体調にお気ををつけてお過ごしください。
先日ゴールデンウィークにお台場へと行ってきました。

こどもの日だったので、娘の一番行きたいとこへと行ってきました。
大好きなひろがるスカイ!プリキュア のイベント『ひろがるスカイ!プリキュアお台場フェスティバル』に行ってきました!!
プリキュアとは、毎週日曜8時30分から9時に放送されている、東映アニメーション制作のテレビアニメ。
毎年のようにテーマやモチーフを変え、未就学の子どもたちに向けたアニメとして放送されて、これまでに世代や性別を超えて多くの方々に人気のアニメです。


ショーやキャラクターとの写真撮影が出来るので娘はとても喜んでました。親は写真撮影に必死でとても疲れましたが。
ゴールデンウィーク、楽しい思い出が出来ました☆
幅広い方で人気のアニメなのでぜひ機会があったら見てください。
全国各地でイベントもやってます。
それではまた。