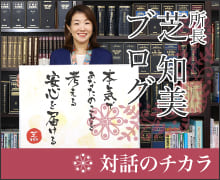Aさんは、自営業(個人事業主)で生計を立てていました。しかし、売り上げが減ってきたためキャッシング等を利用して生活費や事業費を賄うようになりました。今般、返済できなくなってしまったため自己破産を考えています。
自営業(個人事業主)の人が自己破産手続きを行う際に、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
自営業者(個人事業主)の自己破産手続きは、原則として管財事件として扱われます。
管財事件とは、「債務者が財産を持っており、債権者に分配できる財産がある場合の手続き」のことです。自営業者(個人事業主)には、事業に使っていた設備や機械、売掛金(まだ回収していない売買代金等)といった財産があり、それらの財産一つひとつをしっかりと調査する必要があるため、この手続きがとられます。
静岡地裁を含む一部の裁判所では、管財事件を通常の管財事件と小規模管財事件に分けています。小規模管財事件は、財産が少なく迅速に手続きを進められる場合に選択され、通常の管財事件に比べて手続きが簡素化されています。大抵の場合、自営業者(個人事業主)の破産手続きは小規模管財事件となります。
管財事件では、破産管財人(裁判所から選任されて、財産の調査等を行う弁護士)に報酬を支払う必要があり、小規模管財事件の予納金は、30万円程度(静岡地裁の場合)となっています。その他にも、司法書士や弁護士に手続きを依頼する場合には報酬等が必要となります。
そのため、自営業者(個人事業主)が自己破産申立を行う前にはある程度の資金を貯めておく必要があります。
なお、生活保護を受給している場合には、法テラスを利用することで実費と着手金のほかに20万円を上限として予納金の立て替えを受けることができます。
司法書士 廣川祐司